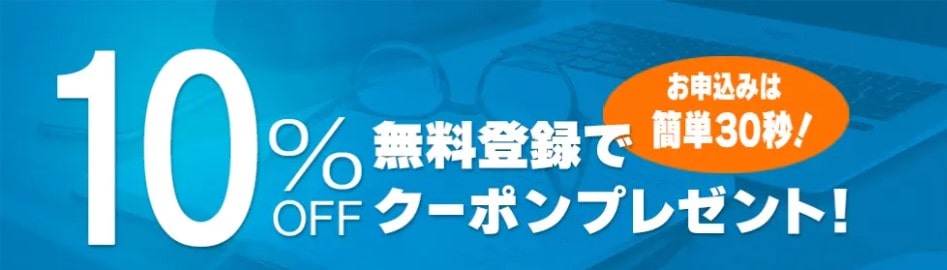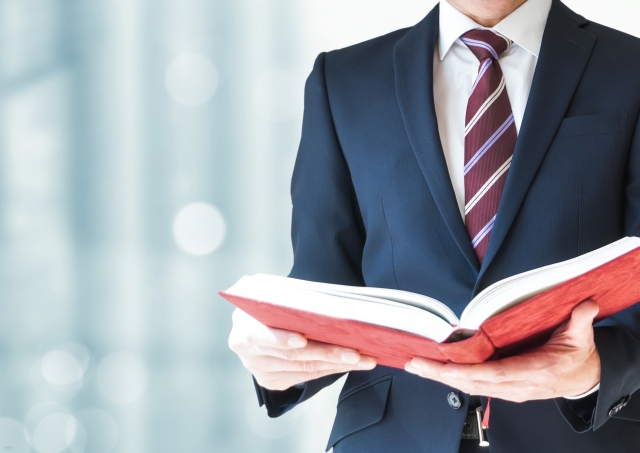Unable to locate payment record.
わたしは受験時代、毎日勉強に明け暮れていました。
講義が終わればすぐに自習室へ、自宅に帰ってまた勉強。平日から土日まで、同年代の皆が遊んでいる中、遊ぶ暇なくひたすら勉強をし続けました。
そして税理士試験は次の通り、傍目に見れば良い結果で終わりました。
1年目:簿記論〇、財務諸表論〇、消費税法〇
2年目:法人税法A、相続税法〇
3年目:法人税法〇 → 5科目合格(当時21歳)
どの科目でも、模擬試験はクラス内で常に上位。最初から最後まで1位争いを続けていました。
業界の中では3年5科目合格、そして21歳での合格というのはかなり早いです。本当によくやったと思います。
しかし、私は法人税法も1発で合格し、2年で5科目合格を果たす予定でした。法人税法の不合格時も、専門学校の合格予想のボーダーラインちょうどだったので、1発で合格できるだけの実力はあったと言えます。
しかし、落ちました。
これだけ勉強して落ちた理由はなぜか、私なりに考えました。
原因は、専門学校への過信。
この一言に尽きます。
不合格だった日は大泣きしましたし、つらくて眠れませんでした。今でも鮮明に覚えています。
もう専門学校は信頼できない。自分で何とかして合格するんだ。この反省に基づいてまずは勉強法を見直しました。
その結果、独自の勉強方法により、翌年には念願の官報合格を果たしました。
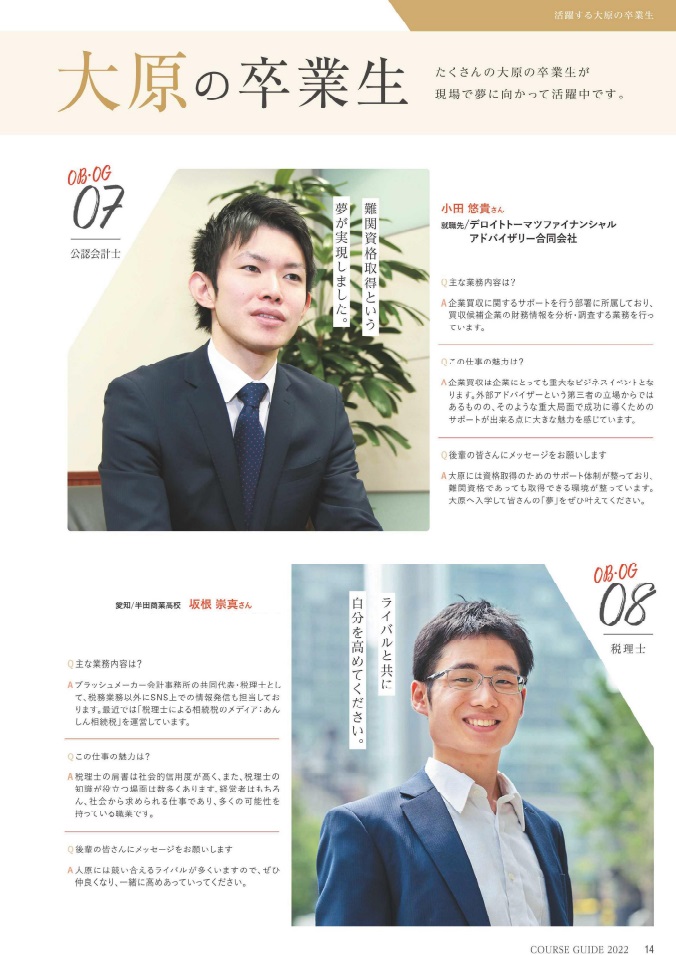
大原のパンフレットにも掲載されました。
このnoteには、私の失敗経験、成功経験を踏まえた、税理士試験を1発で終わらせるためのノウハウが詰まっています。すべて本音で書いており、専門学校等から批判を受ける可能性もありますので、有料にすることでクローズドな情報にしています。
ノウハウを詰め込んだ甲斐もあり、販売開始からたくさんの方にご購入いただいており、高評価をいただいています(2022年6月時点、50名以上の方が購入済みです)。

2021年8月(5,000円販売時期)

2022年1月

2022年2月

2022年3月

2022年5月

2022年6月
最初は5,000円で販売していましたが、ぶっちゃけ5,000円以上の価値はあると思っていますので、今後段階的に10,000円に値上げする予定です。このnoteを読めば、誤った勉強方法をして1年間を無駄に過ごすという私が経験した失敗を避けることができます。
1年間を棒に振りたくない、絶対に合格してやるんだ。
そう考えている方は私に会って焼肉を奢ったつもりで今すぐにご覧ください。
法人税法の不合格体験から言えること
わたしの税理士試験の受験経験は次の通りです。
1年目:簿記論〇、財務諸表論〇、消費税法〇
2年目:法人税法A、相続税法〇
3年目:法人税法〇 → 5科目合格(当時21歳)
人によっては、うらやましいストレート合格に思えるかもしれません。しかし、私としては2年で5科目合格するつもりで勉強していましたし、法人税法の模擬試験では常に上位に食い込んでいて、十分に合格できるレベルでした。
しかし、不合格でした。それはなぜでしょうか。
理由はいくつかあります。
①勉強時間が足りなかった(ただし、勉強につぎ込んだ時間は同期の中では多い部類だったと思います。1日中勉強していましたし、模擬試験でも常に上位にいました。)
②理論の解答を丸暗記でべた書きしたこと
特に、②が大きかったように思います。これは専門学校の模擬試験の採点方法を鵜呑みにしてしまった面があるからです。
専門学校の模擬試験の点数を気にしてはいけません。専門学校の模擬試験は、「講師が採点しやすい問題や配点」になっています。
講師が採点しやすいよう、専門学校の模擬試験では、理論問題の答えを条文丸写しにするような回答を求めています。
ただし、これを試験本番でもやってしまうと不合格になる確率が大幅に上がります。(私は大原とTACのダブルスクールでしたが、特に大原は顕著でした。本試験の解答速報でも理論べた書きの配点であればボーダーラインにはのっていましたが、そういった解答では合格は厳しいです)。
つまり、理論テキストや理論ドクターの丸写しの回答では不合格になる可能性が極めて高いということです。
当たり前ですよね。
お客さんから「〇〇が起こったのですが、✕✕について気を付けなければいけないことはありますか?」と聞かれた際に、「法人税法〇条では~~」と、条文をつらつら述べる人はいません。
「答えがわからなかったら、理論テキスト丸写しの回答をすれば部分点がもらえるから書け」
「理論テキストの丸写し回答を行え。ただし、書いた条文が違っていたら点数ゼロ」
「論理的回答をした部分について配点なし、理論テキスト丸写し部分についてのみ点数あり」
そんなバカな採点をするのは専門学校だけです。
簡潔に「△△なので、〇〇の取り扱いとなる」と述べれば十分に合格できる可能性はありますし、仮に答えが間違っていたとしても、論理的に回答を行っており、一定の根拠があれば部分点は入ると思います。条文丸写しをするとしても、それは後回しにすべきです。
わたしが消費税法・相続税法を受験したときも、時間が足りなかったので条文はあまり書いていませんでしたが合格しました。
そして、2度目の法人税法の受験時(合格したとき)も、条文についてはあまり触れず、「〇〇だから✕✕となる」という論理的回答を行いました。これが不合格にならないために絶対に必要です。どの科目においても。
なお、大原と異なりTACの模擬試験は論理的回答を求めていることが多いです。もし、大原だけしか通っておらず、何年も合格できない方はTACなど他の予備校も通ってみると良いでしょう。
模擬試験だけでも受講できるので、一度はTACの模擬試験だけでも受講してみることをお勧めします。どんな問題が出題されるのか、どんな回答を求めているのか、予備校によって考え方が違います。
(本当はダメなので直接的な表現は避けますが)模擬試験を申し込むお金が無いなら仲間を集めてください。1人で出せなくても、5人もいれば数千円におさまるでしょう。
お金はかかりますが、それで1年を棒に振るよりよっぽどマシだと思います。
繰り返しとなりますが、専門学校の模擬試験の解答や配点は、あくまでも専門学校が採点しやすい形式にしているだけに過ぎません(特に大原生は注意)。受験生が落ちたら再度受講してくれるので、自社の売上になることも期待しているのかもしれませんが、その罠にかかってはいけません。
わたしは理論テキスト、計算テキストすべてのページを頭の中でイメージできるまで叩き込みました。そうすれば、「専門学校の模擬試験で」上位に食い込むことは簡単です。ただ、本番の試験では、必ずしも丸暗記の回答は求められていません。覚えたことをそのまま回答用紙に記載しない方が良いです。
求められていることについて論理的に回答するクセを身に着けることで、税理士試験に合格する確率は高くなり、専門家として働くうえでの基本的な思考も身に着くことでしょう。
余談1:計算根拠は時間がなければ端折ってもいい(と思います)
相続税法や消費税法の試験では、計算根拠を書く欄が大きく設けられています。あくまでも「私はこうだった」としか言えませんが、時間がなければ計算根拠は端折ってもいいと思います。
一つの例ですが、相続税法の試験(計算問題)で、取引相場のない株式の評価方法の判定問題(原則的評価方式 or 特例的評価方式)が出題されました。
大原などの模擬試験だと、こと細かく、同族株主がいる、中心的な同族株主がいる、など順序だてて計算根拠を示す必要があるかと思います。
ただ、結論を簡単に導きだせる要素があるなら、根拠はそれだけ書いてしまって次の問題に移った方が良いでしょう。
明らかに原則的評価方式と判断できる問題に、大原のように計算根拠を書くと10分ぐらいかかりそうでしたので、私は重要な部分だけ書いて1分ぐらいで判定した覚えがあります。
時間が余っているなら別ですが、順序だてて説明しなくても、根拠を1つ説明して、結論がわかっているならそれで充分だと思います。
余談2:テキストを何度も繰り返し読んで覚える、問題集を何度も解くのは有効
わたしは計算テキスト、理論テキストのすべてのページを頭の中でイメージできるレベルまで繰り返し読んで覚え、問題集も同じものを10回は解いていました(自主勉強するだけなら計算過程の記入は時間の無駄なのでメモは最低限しか行わない)。
冗談抜きで、すべてのページを頭の中でイメージできるようにしていました。
色々と手を出すのも確かに良いですが、テキスト、問題集に載っている問題をすべて解けるなら基本はどの科目も合格できます。それで上位10%に入ります。残り90%の人はそこまでやりませんから。
みんなができないことを覚える必要はなくて、みんなができるところ(つまりテキストに書いてあること)を時間内にミスなく解けることが大事です。
データは古いですが、平成9年~11年に、実際に税理士試験の試験委員(簿記論担当)を務めていらした八ツ尾先生の言葉を引用します。
税理士試験委員だった時、サンプリングとして二千人ぐらいの答案を事前に採点した。そこで、合格率を予測し、配点の調整をした。しかし、そのサンプリングを間違えると、大変なことになる。例えば、受験番号の若いところから選ぶと、全体の合格率は下がる。私の3年間はすべて10%を下回った。陳謝。
— 八ツ尾 順一 (@Junichi_Yatsuo) April 15, 2021
私が担当した税理士試験の答案の枚数は、半端でなかった。果てしない採点作業をしている中で、採点者を最も喜ばせる答案は「白紙の答案」である。この答案に出会うと、手を合わせながら、丁寧に「零点」とつける。逆に、適当な数字を書き、すべて誤っているケースは、怒りながらゼロと書き殴った。
— 八ツ尾 順一 (@Junichi_Yatsuo) April 15, 2021
私が受験生であった遠い昔のこと。高名な簿記の大先生が、自分で作った問題を時間内に解くことができなかったという、受験生にとって、笑うに笑えない話を聞いたことがあった。試験問題というものは、結局、競争試験で、他の受験生を見ながら、ひたすら走らなければならないと悟った。どう思いますか?
— 八ツ尾 順一 (@Junichi_Yatsuo) April 15, 2021
みんなができることを、時間内にミスなく解ければ基本は合格できます。
計算テキスト、理論テキストを完璧に覚え、問題集を繰り返す。それだけで基本的には合格できますが、これだけだと落ちてしまったのが法人税法です。
そのため、計算テキスト、理論テキストの精度を高め続けるだけでなく、先ほど説明したように、本番で論理的に回答することだけ意識しておけば、不合格になる確率はさらにグッと下がります。
余談3:実体験談ですが、講義は聞かなくても良いです
わたしは大原の専門課程に通っていましたが、講義はほぼ聞いていませんでした。
具体的に聞いていなかった部分としては簿記論、財務諸表論の後半と相続税法の3分の2、法人税法の2年目です。
どんなに良い教材があっても、教えるのが下手な人はどこにでもいます。もしテキストの読み上げしかしていない先生の講義なら、別に聞く必要はありません。
「人の話を聞かない人は成長しない」とよく言いますが、教える側のレベルが低かったら、いくら聞いても成長することはできません。
もし「この人はダメだな」「この学校はダメだな」と思ったら、自分が合格できると思うやり方でやればいいと思います。
+α:過去問は見ておきましょう
上述したように、税理士試験で大切なのは論理的に回答することですが、それ以上に大事なのは、やはり勉強時間です。私は学生時代、朝から晩まで授業を受け、その後、ほぼ一切遊ばずに勉強していました。それが良いか悪いかは考え方次第ですが、一生に一度ぐらいそんな期間があってもいいのではと思います(10年かけて合格するより、3年で合格した方がいいですよね)。
ただ、闇雲に勉強するのもどうかなという考えはあります。
何をすればいいのかというと、「過去問」を見てください。恐らく、専門学校では「過去問は見なくていい。専門学校のテキストや模擬試験は過去問を考慮して作成されているから」と言われます。ただ、実際の試験で問われた内容に触れることは、ゴールを見据えるために必要なことです。
ゴールを見ずに走っても、方向を間違えればいつまでたってもゴールにたどり着くことはできません。3年分ぐらいは過去問を見て、自分だったらどういう回答をするかという観点を養っておくことは大事です。試験官も、問題を作成するうえでは過去の問題を少なからず参考にするはずです。同じ問題が出題されないにせよ、どういった回答をすれば合格できるだろうかという視点を持つために、過去問を見ておきましょう。
ひとりでも多くの方の税理士試験の合格を願っています。 以上
****ここから先は事務所の求人情報です
【求人】税理士試験受験生も歓迎
働き方を見直しませんか?
新宿税理士事務所では従業員を募集しています。理不尽な顧問先なし、営業なしのデスクワーク求人です。
実際に働くまでは「税理士事務所って普通デスクワークですよね?」と思っていた方も多いと思います。
違いますよね。むしろ、たいていの税理士事務所は外勤型です。
実名を挙げるとベンチャーサポートは明るい体育会系の営業マンしか求めていませんし(毎年数百人採用して9割辞めるようです)、古田土会計も同様です。
顧問先に毎月1人で訪問をし、社長と話しをして事務所に戻る。
それでいて、求められる資格は簿記2級。
世の中そんな事務所ばかりです。
税理士試験の合格を目指す人とは正反対ですよね。
一方で、弊社が求めているのは真面目に書類作業をできる方です。デスクワークでOKです、顧問先に1人で行く必要はありません。
お客さんには事務所に来ていただくか、面談をするにしてもZoomなどオンラインミーティングで済ませます。顧問先からの日々の相談対応は、私を含めたChatwork(LINEのビジネス版のようなもの)で行うので、事務所に行く必要が無い日はリモートワークもOKです。
残業少なめ
弊社の顧問先は決算月がバラバラなので残業は少なめに済みます。
個人事業主は毎年3/15が絶対の期限であり、法人の申告期限は決算期から2か月以内です。そのため、よその事務所では12月決算、3月決算が多めになるため1月~5月、6月ぐらいまで死ぬほど忙しくなる、というケースがほとんどです。
しかし、弊社の場合、法人の顧問先は決算月をずらしてもらい、3月決算~10月決算までバラバラです。
繁忙期、閑散期の差を少なくすることで多くの件数を担当できるようにしているため、極端に暇な月というのはありませんが、繁忙期に死ぬほど忙しくて1か月休みなし、3日間連続で徹夜(これはいずれも、私がかつて勤めていたときに毎年のようにあった出来事です)、という事態にならないようにしています。
さらに、給与計算、年末調整などは社労士さんに対応していただくので、他の事務所と異なり12月も比較的余裕があります。
弊社の報酬単価は高くありませんが、決算月がバラバラ、かつ、顧問先への訪問を行わないことで1社あたりにかける時間を減らして利益率のバランスをとっています。
こういった取り組みによって長時間残業にならないようにする予定(繁忙期以外、原則0~月20時間に抑える予定)であり、試験期間前の有給休暇も柔軟に対応します。
仕事の担当はどんな業務?
担当していただく業務は、個人事業主や従業員~5名で売上3,000万円未満程度の中小企業の決算、申告書作成業務、お客さんの応対業務がほとんどです。
2022年3月現在、従業員50~100名規模の大手事務所並みに毎月20件~50件近くの問い合わせをいただいています。あまり変なお客さんとは契約しないので、お客さんの人柄は良い人ばかりです。
上述したように、残業は少なめにする予定です。ブラック事務所にするつもりは一切ないので、全部受注するわけではありません。スタッフの業務状況に応じてと考えています。
ちなみに、組織再編や連結納税といった複雑な案件は受けていません。そもそも依頼が来ないですし、やりませんか?と言われたとしても正直受けない可能性が高いです。複雑な税制を経験してみたい、という方はBig4に行きましょう。
高度な税務というのは一発ミスれば数千万円、数億円の賠償問題に発展しかねませんので、正直リスクが高すぎです。
リスクを減らすために検討を多く重ねるわけですが、結果、営業時間外に勉強(実質、サービス残業)が必要になったり、たいして調べもせずに上司に報告をすればちゃんと検討したのか?と怒られる世界です。
うちではルーチンワークがメインになるので、穏便にいられるわけですね。
給料は?
事務所経験者であれば前職給与保障、未経験の場合は簿記2級なら月18万円、税理士試験3科目なら月21万円です。残業代は別途で賞与は基本給の3か月分です。
少ないと思うかもしれませんが、他の税理士事務所だとみなし残業40時間など平気でぶち込んでおり、みなし残業を控除すると上記の給料と同レベルもしくはこれより低いことも少なくありません(さらに、最低でもみなし残業の時間分はきっちり働かせられる)。
また、事務所の未経験者は1年目は戦力になりませんので、残業代をきちんと支払う、有給休暇をきちんととってもらうことを考えるとむしろ事務所としては赤字なぐらいです。
事務所を経営するうえでは、やはり給料の3倍程度の売上分の顧客対応はしてもらわないといけないです(経費も、会計ソフト1人分で年間20万円、パソコンも20万円、事務所のWifiや事務所家賃、コピー代など毎月15万円以上など、結構お金がかかります。決算書、申告書の精度が完璧じゃないなら所長税理士の時間も多く使うことになります)。
弊社では顧問先の報酬単価を今後どんどん上げていきますし、対応できる社数が増えて担当の売上が増えたり、精度高く決算書、申告書を作成できるようになればその分は給料に還元していきます。
長く勤めてくれる方募集です。
「就職・転職はまだ先だけど事務所見学してみたいな」という方はフォームからその旨メールください。東京の新宿駅から徒歩5分程です。