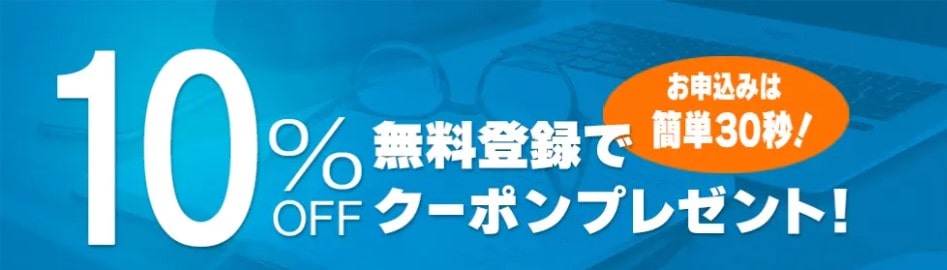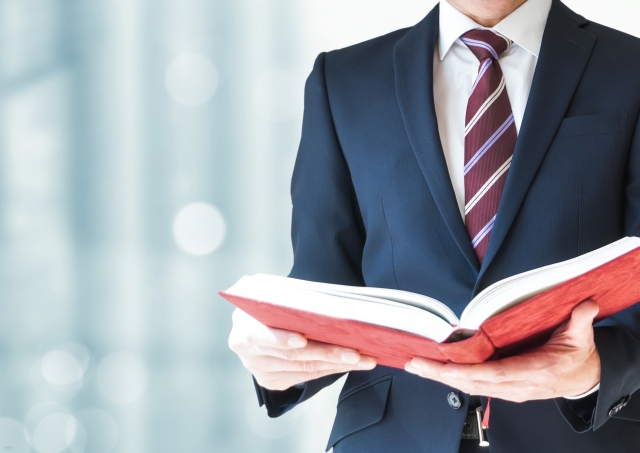税理士試験の合格を目指すなら、まずは大原が選択肢にあがります。学費は高いですが、合格実績十分であり、本気で合格したいなら選択肢として申し分ありません。
この記事では、大原に通い、税理士試験に3年5科目合格した税理士の坂根が解説します。
ポイント
- 大原の税理士試験合格者占有率は約60%
- 大原の講師の質は平均するとそれなりに高い
- テキストはわかりやすい
- 合格したいなら大原は第一候補
- 料金は安くないので、通信講座が選択肢にあがるならスタディングもアリ
税理士試験に強いと評判、資格の大原(大原簿記)とは?
資格の大原(大原簿記)は、全国100か所以上に校舎を構える専門学校(予備校)です。
歴史も長く、1957年に東京の水道橋に大原簿記学校を開校したのが始まりです。
始まりが簿記の学校なため、簿記検定での合格者はもちろん、税理士試験や公認会計士試験の合格者も数多く輩出しています。
資格の大原で税理士試験は合格できる?
資格の大原で税理士試験は合格できます。
毎年、5科目合格(官報合格者)の半数近くは大原から輩出されているため、今まで税理士になった人の半分近くは大原で勉強した経験があります。
2020年度第70回税理士試験の官報合格者占有率は57.5%(※)と公表されており、10年以上前から50%ぐらいを占めている(60%超えの年もある)と記憶しています。
※URL:https://www.o-hara.jp/course/zeirishi/zei_feature_01
資格の大原(大原簿記)の特徴
資格の大原(大原簿記)について、次の3点解説していきます。
ポイント
- 講師の質の平均はそれなりに高い
- テキストはわかりやすい
- 料金は安くはない
講師の質の平均はそれなりに高い
資格の大原の講師の質の平均はそれなりに高いです。
もちろん、人によってばらつきがあり、税理士試験の勉強を教えているといっても、その科目に合格していない方もいます(他の予備校も同じですが)。
ただし、講師陣は熱意ある方が多いです。
大原の税理士講座を選んでよかった、さっき一度だけ受講相談でお時間もらった先生から「コロナだけど勉強大丈夫ですか?簿記1級中止になっちゃったけど頑張れてますか?全経はまだあるみたいだから頑張りましょうね」ってメールが来ててちょっと泣けた、早く通いたいな
— ももこ (@Momo051243) May 7, 2020
大原の先生方本当にありがとうございました❗
これからは一流の税理士を目指し頑張ります。— JUN@税理士 (@jun4567jpn) December 23, 2018
この熱意があるというのは大原の大きな特徴の1つです。
大原では、高校卒業後に大学のように通う「専門学校」としての顔も持っています。
2年制課程や4年制課程などがあり、いずれも全日制課程(平日毎日通う)です。そのため、中学校や高校のように、生徒に対して愛着を持っている方が多く、生徒の合格を応援したいという文化が根付いています。
1人で勉強するのがむずかしいな、合格を応援してくれる先生のもとで学びたいな、という方にとっては、大原は良い学校だと思います。
テキストの質は良い
資格の大原のテキストの質は良いです。
最低限抑えなければならないことを、わかりやすくまとめています。
税理士になったあとも、基本的なことを調べたいときの参考にする方も少なくありません。
わたしは大原とTACの両方に通った経験がありますが、テキストのわかりやすさで言うと圧倒的に大原の方が良かったです。
TACは、税理士としての仕事でさえ一生に一度も目にする機会が無いような細かいところまでテキストに書いてあったり、メリハリがない印象があります。大原のテキストは、わかりやすくコンパクトにまとまっています(それでもかなり分厚いです)。
だいたい各科目、計算テキストが4冊ぐらい、理論テキストが1冊の計5冊あります。テキストがわかりやすいかどうかは重要なポイントなため、その点で言えば大原は安心です。
料金は安くない
資格の大原の税理士試験の料金は次の通りです。
2021年9月開講 初学者一発コース
(単位:円)
| 科目 | 教室通学・映像通学 | Web通信 | DVD通信 | 資料通信 |
| 簿記論 | 230,000 | 215,000 | 268,000 | 129,000 |
| 財務諸表論 | 230,000 | 215,000 | 268,000 | 129,000 |
| 所得税法 | 251,000 | 236,000 | 290,000 | 140,000 |
| 法人税法 | 251,000 | 236,000 | 290,000 | 140,000 |
| 相続税法 | 251,000 | 236,000 | 290,000 | 140,000 |
| 消費税法 | 155,000 | 140,000 | 172,000 | 91,000 |
| 国税徴収法 | 155,000 | 140,000 | 172,000 | - |
| 住民税 | 155,000 | 140,000 | 172,000 | - |
| 事業税 | 155,000 | 140,000 | 172,000 | - |
| 固定資産税 | 155,000 | 140,000 | 172,000 | - |
| 酒税法 | - | - | - | - |
図:大原の料金表から作成
DVD通信だと、教室通学より高いですね。酒税法は受験範囲が狭いため、9月開講は無いようです。
なお、基本的には受験範囲の広さに応じて価格設定されています。
税理士試験は1年に1回8月に行われる試験ですので、試験直後、9月から受験勉強を始めるのが一般的です。
そのため、この料金が一般的なコースの料金です。
2021年1月開講 初学者短期合格コース
税理士試験は毎年8月に行われ、結果発表は12月に行われます。そのため、結果発表が終わった直後、1月から勉強をスタートするというコースもあります。
(単位:円)
| 科目 | 教室通学・映像通学 | Web通信 | DVD通信 | 資料通信 |
| 簿記論 | 168,000 | 158,000 | 196,000 | 110,000 |
| 財務諸表論 | 168,000 | 158,000 | 196,000 | 110,000 |
| 所得税法 | 168,000(教室通学なし) | 158,000 | 196,000 | 110,000 |
| 法人税法 | 168,000(教室通学なし) | 158,000 | 196,000 | 110,000 |
| 相続税法 | 168,000 | 158,000 | 196,000 | 110,000 |
| 消費税法 | 150,000 | 140,000 | 172,000 | 91,000 |
| 国税徴収法 | 106,000 | 96,000 | 128,000 | 63,000 |
| 住民税 | 106,000 | 96,000 | 128,000 | 63,000 |
| 事業税 | 106,000 | 96,000 | 128,000 | 63,000 |
| 固定資産税 | 106,000 | 96,000 | 128,000 | 63,000 |
| 酒税法 | 106,000 | 96,000 | 128,000 | 63,000 |
図:大原の料金表から作成
所得税と法人税はボリュームが多く、スケジュールが厳しくなるためか、初学者向けで1月開講の教室通学は無いようですね。
どの科目も、9月開講から4か月あくため、料金はその分安く設定されているようです。
ただ、受験勉強は早く始めた方が合格できる可能性は高くなるに決まっています。
本気で合格したいなら9月開講で申し込むのが良いでしょう。
資格の大原の口コミ
大原は、次の通りわかりやすいというコメントが目立ちます。
今、大原の税理士入門講座を受けていて思ったことが、業界大手の予備校は授業もわかりやすいし、授業後の課題も明確。これなら、去年から授業取っていればなぁと後悔😅
— マロン@税理士試験 (@biFe6TgDrYW6pj7) January 5, 2021
税理士試験終わったらこれだ‥。
大原のテキストってわかりやすいんだなとしみじみ🥲— なつ@簿財2022受験 (@Natsu4802) May 16, 2022
21時からパソコンで大原の法人税の先生を呼びます。とってもわかりやすい先生で良かったです。8月まで頑張れそうです。税理士試験
— snowman (@SNOWMAN2624) October 5, 2014
実際に仕事で読む書籍等と比べると、大原のテキストは圧倒的にわかりやすくまとめられています。税理士試験に合格したいなら、大原に通っておけばまず間違いはありません。
資格の大原に、まずは無料で資料請求

資格の大原(大原簿記)のデメリット
資格の大原のデメリットは、料金が高めであることです。
お金をかけたくないのであれば、スタディングなど、格安の通信講座が選択肢にあがります。数万円で講義にテキスト、問題集に模擬試験までついており、正直安すぎです。
予備校選びに迷ったら、検討してみても良いでしょう。